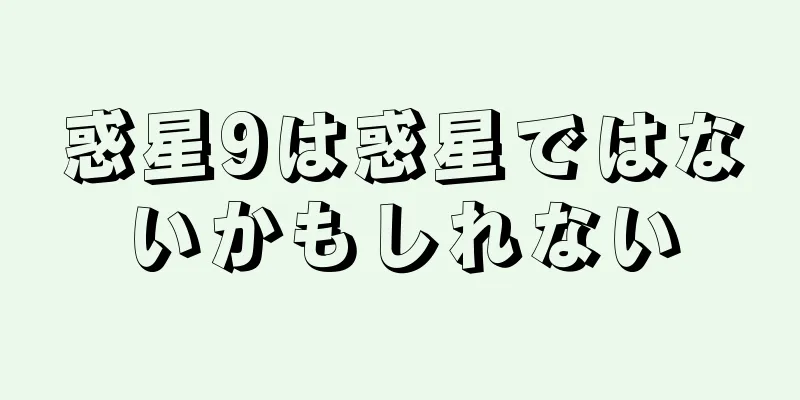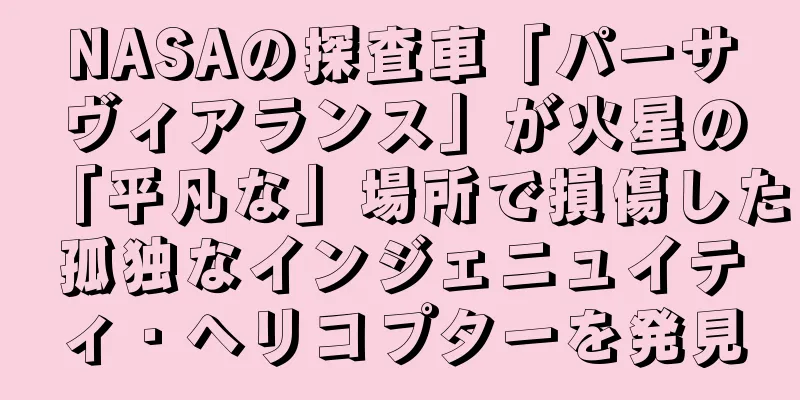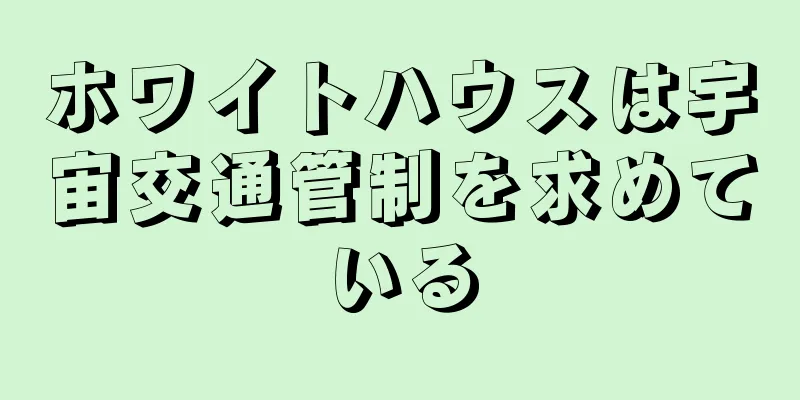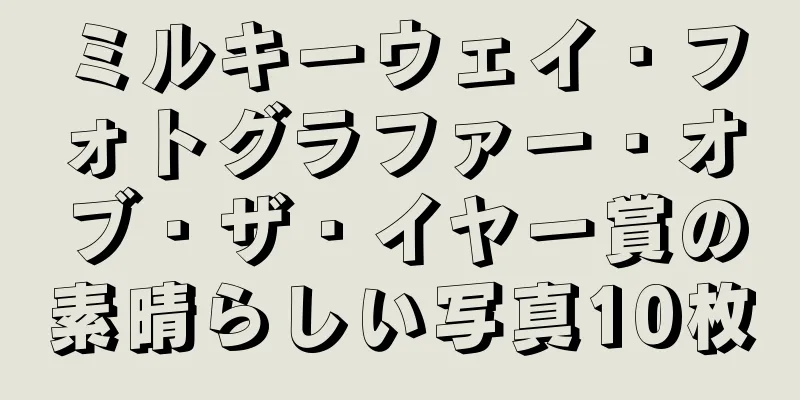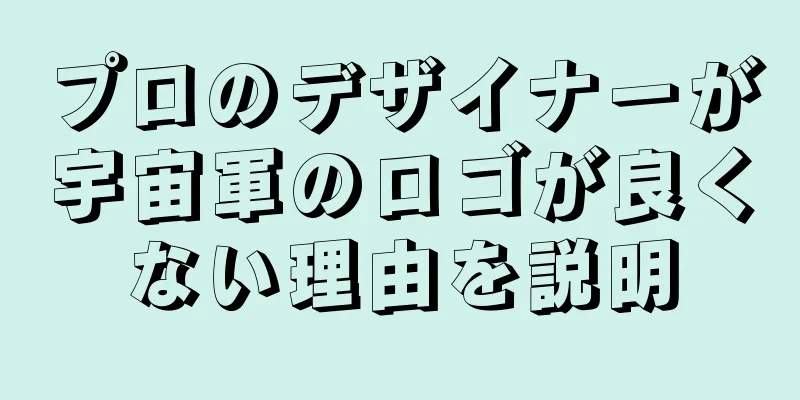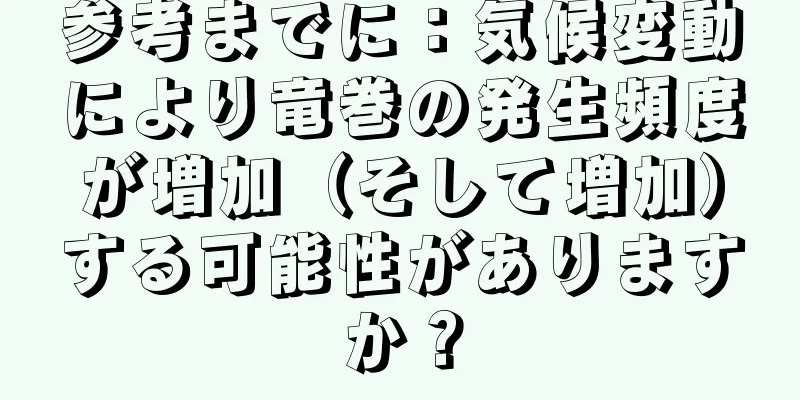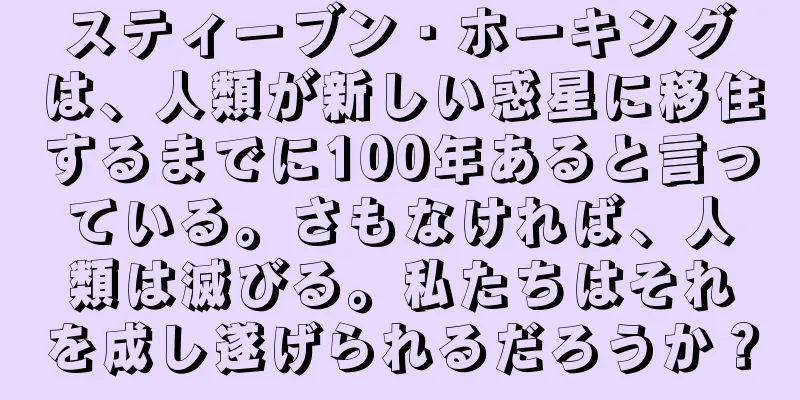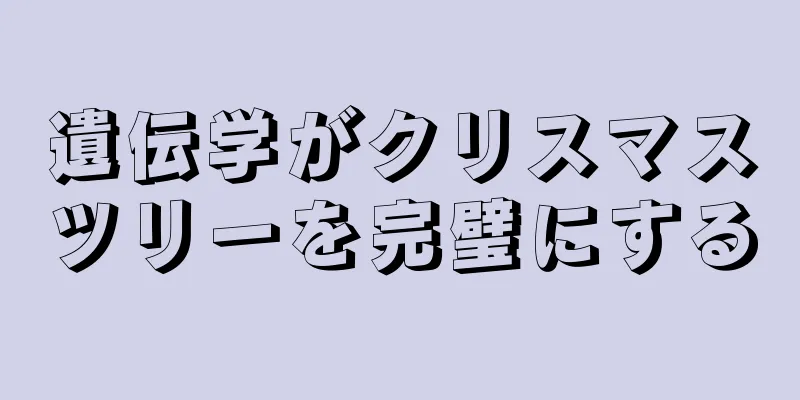「ディフェンダーズ」:SF特集からの抜粋

|
これは、Popular Science の特別号「 Dispatches From The Future」からの抜粋です。iTunes にアクセスして、この号を iPad にダウンロードするか、抜粋リストに戻ってください。 瞬く間に、ライラは外界との連絡が一切途絶えた。沈黙は衝撃的で、孤立感は不安をかき立てた。それは、ジェット機がディフェンダーズの覆いを破り、オーストラリア領空に入ったことを意味していると彼女が知っていたためでもある。彼女はしばらくの間、前の座席の背もたれ越しに見える、はぐれた白髪の束をぼんやりと見つめていた。それはインド大使のガヤトリ・ナダルだった。それから彼女は窓の外を見ようと考えた。 まだ何も見えません。彼らはまだ煙のような雲の上にいました。オーストラリアがあそこにいるなんて信じられませんでした。過去 28 年間、オーストラリアはライラの心の中でほとんど神話的な様相を呈していました。そして、今にもオーストラリアが見えて、それがどうなっているかを見ることになると思うと、彼女の心臓はドキドキしました。 リラの隣の席に座っていたスペイン大使は、初めて彼女に気づいたかのように振り返った。「緊張してる?」 彼女はうなずいた。その言葉はライラが感じているものの陰影や層を表現するには不十分だったが、大まかな近似値としては十分だった。 スペイン人の白い眉毛がひきつった。「ルイテンが侵攻してきたとき、あなたは生きていたのですか?」ボリバル:彼が話しているとき、彼女の頭に彼の名前が浮かんだ。「ディフェンダーを見たことがありますか?」 ライラは笑った。彼が彼女を褒めようとしているのか、それとも本当に彼女がまだ20代だと思っているのか、よくわからなかった。「ああ、ディフェンダーズは見たことがあるわ。あとルイテンもね。」彼女は口を閉じた。その話題について彼女が言いたかったのはそれだけだった。飛行機の中で最年少のアンバサダーだった彼女が最も望んでいなかったのは、飛行機の中で動揺して未熟な印象を与えることだった。 「ああ。ごめんなさい」彼は彼女の表情を読みながら言った。「まだ若い女の子だったのか?ごめんなさい」 2 度目の謝罪は、間違いなく、辛い話題を持ち出したことに対する謝罪だった。相手がその話題に納得できるかどうか確信が持てないのに、ルイテン侵攻について話すのは失礼だった。 「大丈夫。侵略の記憶がない人なんているの?」彼女は無理やり笑顔を作り、窓の方を振り返ったが、もう遅かった。彼らがオーストラリアに向かって突進し、人類が28年ぶりに救世主と接触したとき、ライラの記憶がよみがえった。彼女は、空から落ちてくる巨大なヒトデのようなルイテンが、一方向にくるくると回り、5、6、7本の不完全な付属肢の先端から致命的な閃光を放っているのを見た。ライラは肘掛けをぎゅっと握りしめ、記憶をそのままにして、必要なら展開させようとした。抵抗すれば、より深く引き込まれ、本格的なフラッシュバックに変わり、PTSDモードに入ったら、大使館が最初の機会に彼女を連れ戻すかもしれないことを彼女は知っていた。 彼女は呼吸に集中し、滑らかで均一な呼吸を保った。爆発で地面が揺れ、ルイテン家の電気火が燃える汗のような悪臭を放つ中、7歳の自分が高校の避難所に駆け込む姿を思い浮かべた。 彼らはどこにいる?ディフェンダーズはどこにいる?誰かがカフェテリアに集まり、外で防御を固める人間の兵士たちを見ながらそう言った。兵士たちは、何をしてもルイテンが一歩先を行くことを知っているので、武器をあちこちに向けていた。 そして、間近で初めてルイテンを目にした。ライラが予想していたよりもずっと大きく、3本の腕で木から飛び出し、ブランコや滑り台を駆け抜け、自由な腕は前を向いていた。目もくらむような閃光、ほとんど反対を向いていた燃える兵士たちの叫び声。自分の考えをすべて知っている敵とどうやって戦えばいいのだろう? 森からさらに6匹のルイテンが飛び出してきたとき、ライラは目をぎゅっと閉じていた。彼女は何か楽しいことを考えようとした。お気に入りのテレビ番組、マーメイド・フロリー・ショーだ。彼女は目を閉じて、ショーが終わるまでそのことだけを考えようと決心した。 その後、父親が他の親たちと一緒に外に駆け出し、ルイテンと戦った。兵士たちは全員死んでおり、ルイテンが迫っていたからだ。両親は、焼け焦げた兵士たちの死体の間に武器が横たわっている間に合わせの掩蔽壕にたどり着こうとしていた。社会科の先生、スッチー先生が突進してくるルイテンに消防斧を振り回し、繊毛で胸を真っ二つに切り裂いたことを彼女は思い出した。 そして、暖かいおしっこが彼女の太ももを流れ落ちたとき、あの水っぽい声、あのありえないアクセントが外からこう呼びかけた。「もうすぐ終わるわ。マーメイド・フロリーのことを考えて。もうすぐ終わるのよ。」 ライラの母親は目を覆った。震える指では十分な作業ができなかった。なぜなら、ライラはママの指の間を見て、ルイテンがパパの腕を引き抜いたときにパパの肩関節を見たからだ。彼らのずんぐりとした指のない付属器官は、先端の繊毛が長くて力強い指のように機能していたため、欺瞞的だった。 そして、歓声が上がった。学校の屋上から2人のディフェンダーが飛び降りたのだ。信じられないほど背が高く、節くれだった3本の骨のような白い脚を持ち、自動小銃で砲弾ほどの大きさの弾丸をルイトンにぶちまけ、鋭い外骨格でルイトンが格闘する中、体中を切り裂き、蒸気を発する緑色の粘液を校庭に撒き散らした。生き残ったルイトンが逃げ出し、ディフェンダーが追うと、歓声は倍増した。 ライラはため息をつきながら深く息を吸った。彼女が最後に本格的なフラッシュバックを経験してから 4、5 年が経っていたが、それは避けられないことだった。ディフェンダーズを見て、実際にその巨大なものの前に立って彼らと話をすれば、記憶が甦るのは必然だった。しかし、ディフェンダーズがどのように暮らしていたか、彼らがどのような社会を築いていたかを最初に知ること、そしてついに彼らに個人的に感謝する機会を得られたことは、それだけの価値があった。 引き続きお読みになるには、iTunes にアクセスして、_Dispatches From The Future_ 特別号_ を iPad にダウンロードしてください。 |
<<: 赤ちゃんはみんな同じように見えますか?それはあなた次第です。
>>: 木曜日の振り返り: デジタル写真共有、コンピュータウイルス、そしてラップトップの台頭
推薦する
冷たい新しい宇宙望遠鏡画像で渦巻き銀河の不気味な「骨格」を見る
骸骨の中には、怖いというよりキラキラ輝くものがあります。遠く離れた銀河の新しい画像を見ると、渦巻き銀...
サヴァントのマスターメモリー
キム・ピークレインマンのモデルとなったピークは、本の 2 ページを同時に (両目で 1 ページずつ)...
大腸菌細胞に「Doom」を作用させる…非常にゆっくりと
「 Doom を実行できるか?」というのは、インスピレーションそのものと同じくらい古いプログラミング...
健康的な食生活で甘いものを食べる方法
デザート(または添加糖分を含むあらゆるもの)を食べる最も健康的な方法は、食べないことです。そうは言っ...
NASAの先駆的な宇宙ステーション、スカイラブを振り返る
22年以上にわたり、宇宙飛行士は国際宇宙ステーションに継続的に滞在しており、この軌道実験室は史上最長...
風力タービンがコウモリや鳥を殺すと、科学者たちは死骸を欲しがる
この記事はもともとUndarkに掲載されたものです。 「これは最も臭いの少ない死体の一つだ」と、トッ...
象のパンパは人間の真似をしてバナナの皮をむくことを学んだ
ほとんどの霊長類と違い、ゾウは皮をむかずに喜んでバナナを食べる。しかし、ベルリン動物園のパン・ファと...
今週学んだ最も奇妙なこと:自分の双子を食べること、防腐処理されたミルク、空中に浮かぶカエル
今週学んだ最も奇妙なことは何ですか? それが何であれ、PopSci の最新のポッドキャストを聞けば、...
猫のDNAは猫がおやつから学ぶように進化したことを示す
猫は自分の歴史(歴史?)について多くを語ってくれないが、その遺伝子は語ってくれる。今日、国際的な遺伝...
AmazonがAlexaを宇宙向けに準備している様子を覗いてみよう
SFにおける音声制御の人工知能に関して言えば、AmazonのAlexaのようなスマートスピーカーは賛...
私たちが日常的に誤って食べている信じられないほど不快なもの
毎晩8匹のクモを飲み込むという考えは、インターネットの黎明期に広まった一連のランダムな「事実」によっ...
次のレザージャケットはキノコから作られる
マイコワークス 菌糸体レザー マイコワークス私は何年もの間、バイオテクノロジーが革の生産から牛の飼育...
トレックの新しい自転車用ヘルメットは脳の保護液を模倣している
サイクリングには、フレーム、コンポーネント、さらにはライクラベースかどうかにかかわらず、ウェアなど、...
汚れを好むバクテリアが貴重な芸術品を救うかもしれない
細菌は過小評価されています。農業から風味付けまで、これらの微生物はおそらくあなたが気づいていない方法...
戦ったら、冷血の恐竜と温血の恐竜のどちらが勝つでしょうか?
恐竜は「冷血」だったのか「温血」だったのか?古生物学者はまだ確信が持てない。現在、ある環境科学者が、...