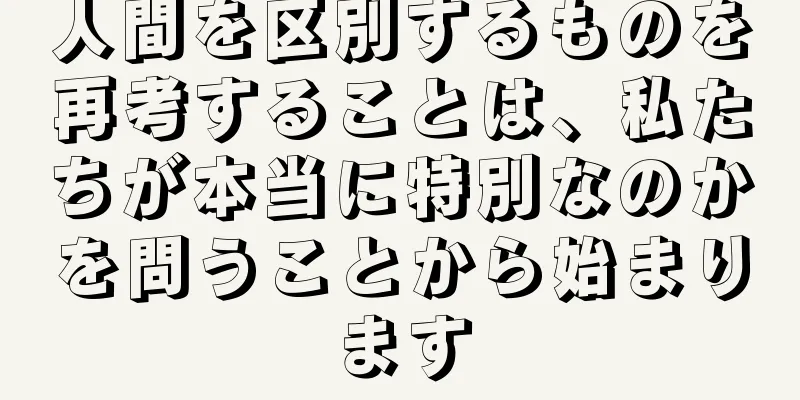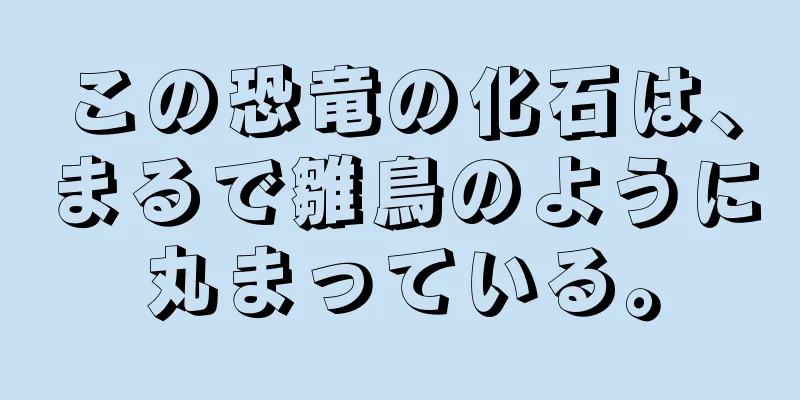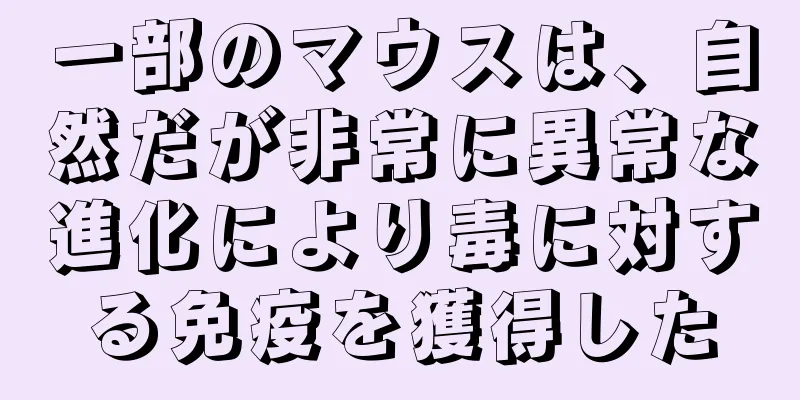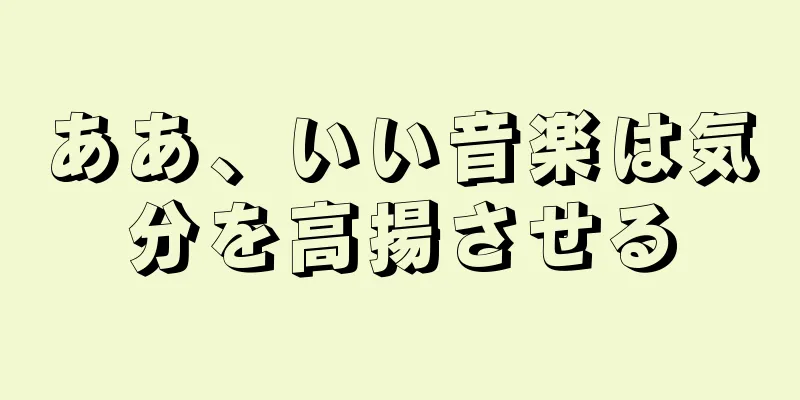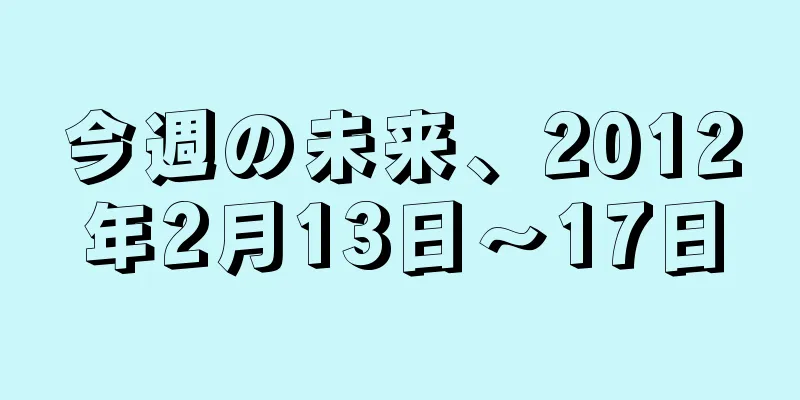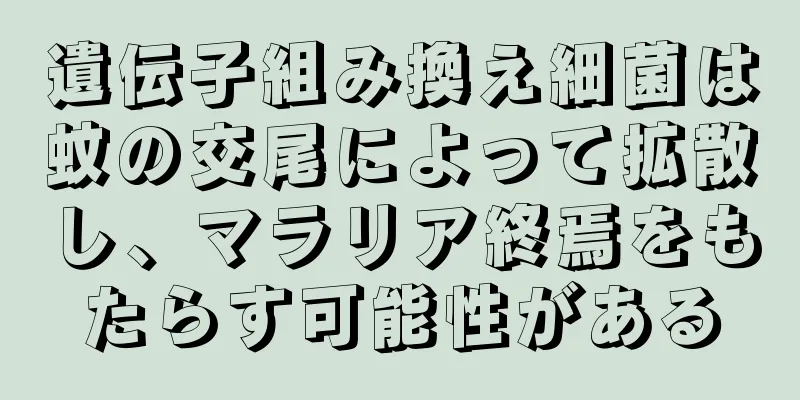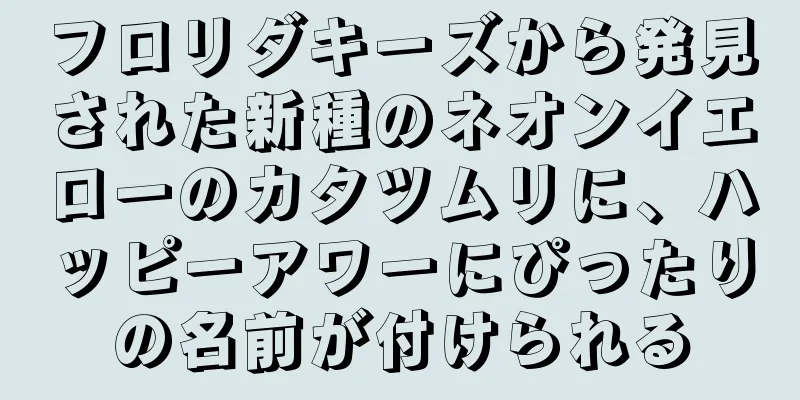冥王星は秘密の海をどうやって温かく保っているのか
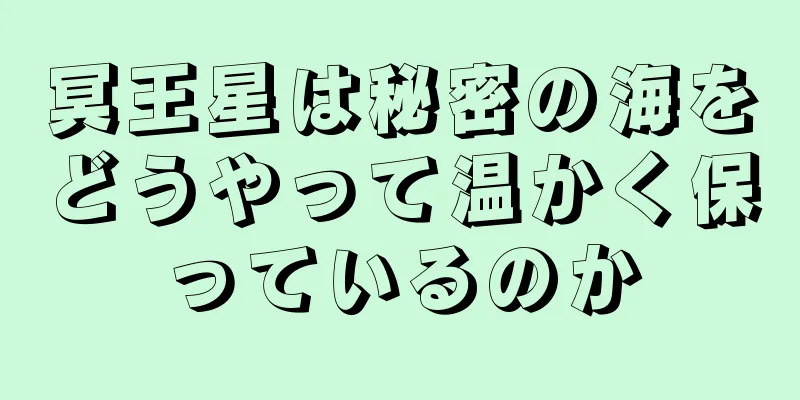
|
科学者たちは近年、冥王星の氷の表面の下に液体の水の海が存在する可能性を示す証拠をどんどん集めている。これは、地球のほぼ 40 倍の距離を太陽の周りを回り、気温が華氏マイナス 380 度を下回る準惑星にとっては突飛な見通しだ。こうした状況から、厳しい疑問が浮かび上がる。冥王星の地下海が本当に存在するとしたら、どうして凍らずにいられるのか? 魔法瓶が温かいコーヒーを外界の冷たい要素から守るように設計されているのと同じように、冥王星もその地球全体の海を(比較的)暖かく保つための独自の断熱策を講じている。月曜日にNature Geoscienceに発表された研究で、惑星科学者チームは、準惑星の表面の氷の殻の真下にガスの層が存在する可能性が高いことを実証した。この層は海を温める断熱材となり、物質が液体のままであるのに十分な温度を保つことができる。この発見は、多くの矛盾する謎を解決し、太陽系で最もエキゾチックな天体の 1 つである冥王星の表面下で何が起こっているのかを科学者がこれまでで最もよく説明することに役立つ可能性がある。 地下海の存在を直接観察したことはないが、その存在を裏付ける証拠は主に 2 つある。第一に、理論計算によると、冥王星内部の岩石の放射性崩壊によって、地下海を維持するのに十分な熱が発生する。第二に、海の再凍結によって生じた亀裂など、地下海と一致する地質学的特徴があること。 冥王星で最も印象的な領域の一つはスプートニク平原と呼ばれる、赤道近くの大きな盆地で、冥王星の有名な淡い「ハート」表面構造の西側のローブがある場所です。高密度の領域でない限り、赤道近くに盆地は形成されません。スプートニク平原は穴なので、塊は地下にあるはずです。また、氷は水よりも密度が低いので、薄い氷の下に深い液体のプールがあるのは理にかなっています。したがって、冥王星のどこかに地下の水の貯留層があるとすれば、スプートニク平原は探すべき場所です。 鎌田俊一氏が考えていたのはまさにそれだった。科学者がまず矛盾を解決できれば、と。北海道大学を拠点とする研究者で、この新しい研究の筆頭著者である鎌田氏は、冥王星に海があるのは、冥王星の内部が温かいことの証だが、もし内部が温かいとしたら、冥王星の氷の殻は簡単に変形できるほど柔らかくなり、殻が均一な地球の形に変形できるほどの氷の流れが生まれるはずだと述べている。スプートニク平原の存在はこの予想に反しており、鎌田氏と彼のチームはその理由を知りたいと考えていた。 カリフォルニア大学サンタクルーズ校の惑星科学者で、この研究の共著者であるフランシス・ニモ氏は、彼と他の研究者は、海の存在は海に不凍液の性質を与え、氷の流れを妨げているアンモニア濃度と関係があると信じていたと語る。「それは皆を少し不安にさせました」とニモ氏は言う。「そんなに多くのアンモニアが存在する可能性は低いです。ですから、この新しい研究は、海に大量の不凍液を投入することなく、氷の流れのなさを説明する試みでした。」 鎌田氏は、さまざまなプロセスをすべて調和させることができるモデルを見つけようと取り組み、最終的に、計算ではガスの存在を考慮する必要があることに気付きました。 「断熱」と言えば、何が起こっているのか簡単に理解できますが、ガスが、たとえば乾式壁の内側に詰め込まれた断熱材と同じメカニズムで機能しているわけではありません。氷が形成されると、その分子構造は凝固し、結晶構造に膨張します。ガス分子は、クラスレートと呼ばれる氷の「ケージ」内に閉じ込められることがあります。クラスレートが形成されると、氷の断熱特性が 10 倍以上になります。クラスレートは、海を暖かく保ち、氷の殻を冷たく保ち、氷の流れを防ぎます。 「クラスレートは普通の氷とほとんど同じように見えますが、火をつけるととてもよく燃えます」とニモ氏は言う。これらのクラスレートのガス分子はメタンであると考えられており、その大部分は水に囲まれている。クラスレートは、氷の殻が徐々に厚くなるにつれて下から泡立つメタン分子を捕らえて形成されると考えられる。「ガス分子がどこから来るのかは良い質問です」とニモ氏は言う。「それらは冥王星が最初に形成されたときに残ったものか、または冥王星のケイ酸塩核が温まるにつれて反応して形成された可能性があります。」 鎌田、ニモ、および同僚らは、冥王星内部の温度の変化と氷の表面殻の形状の変化を考慮したコンピューターシミュレーションによってモデルを検証した。クラスレートがなければ、海は10億年前に凍結し、氷殻はその後すぐに平らになっていただろう。「巨大な彗星のような物体に変わっていたかもしれない」と鎌田は言う。むしろ、このメカニズムは地下海の将来にとって朗報であり、おそらく今後数十億年は海が液体のままであり、表面の氷は釘のように頑丈に保たれるだろう。 これは素晴らしい説明だが、これらのモデルはあくまでもモデルであり、証明ではない。「地下の海を検出するためによく使用される、より決定的なテストがありますが、現時点では、データがないか、冥王星が協力してくれないため、どれも実行できません」とニモ氏は言う。「たとえば、磁気誘導シグネチャを探して海を検出することはできますが、冥王星には磁場がありません。あるいは、測定された重力と地形を比較して海を探すこともできますが、そのためには軌道上の宇宙船が必要です。」 たとえ海があったとしても、潜在的なガス緩衝帯自体を研究するのはさらに難しい。スプートニク平原は質量過剰の領域なので、軌道上の機器を使用してその周囲の重力場の変化を測定できる。そして原理的には、非常に強力なレーダーシステムがあれば(将来のエウロパ・クリッパー・ミッションが木星の衛星を研究する際に搭載されるもの)、氷殻を通してガスを画像化できるかもしれない。さらに、冥王星の大気圏を飛び回るガス分子を測定することで、閉じ込められたクラスレートのヒントさえ得られるかもしれない。しかし全体として、数十億マイル離れた100マイルの氷床の真下にクラスレートのコーティングがあることを証明するのは決して簡単ではない。 しかし、少なくとも科学者たちは、何に焦点を当てるべきかについて、もう少し方向性が定まった。冥王星は内部に何かを隠しており、深宇宙科学の新時代が遅かれ早かれそれが何であるかを明らかにするはずだ。 |
>>: 純粋な「火球」隕石には地球外有機化合物が含まれている
推薦する
今日、健康と科学の世界で起きている日食以外の7つの出来事
今日、月が太陽の光を一時的に遮り、それが国内の多くの場所で観測される。これはエキサイティングでクール...
ネアンデルタール人と現代人は4万5000年前にヨーロッパで混ざり合った
約10年前、ネアンデルタール人がホモサピエンスと交配したという説が アフリカ以外でのこの発見は、人類...
チャールズ・ダーウィンの進化論はガラパゴス諸島よりも彼の庭に負うところが大きい
これは科学における最も偉大な物語の一つであり、ニール・アームストロングの月面への小さな一歩やジェーン...
この休暇中に家族に伝えたい 12 の奇妙な科学事実
以下は、上のビデオのスクリプトです。よろしければ、ぜひご覧ください。音声なしで情報を見たい場合は、こ...
いつもより花火の音がよく聞こえるのはなぜでしょうか?
ジェイ・L・ザゴースキーはボストン大学クエストロム経営大学院の上級講師です。この記事はもともと Th...
ウォーリー・シラーやトム・スタッフォードのように、レディー・ガガも宇宙でパフォーマンスを披露する
レディー・ガガは、生肉で作ったドレスを着たり、今年のMTV VMAアワードショーをほぼ全裸で観たりと...
月は私たちが考えていたよりも4000万年古い
月は宇宙で最も近い隣人であり、人類が足を踏み入れた唯一の天体ですが、私たちはまだ月について学んでいま...
アマチュアがロボット望遠鏡を通して天文学を観察できるグローバル天文学ソーシャルネットワーク
望遠鏡を所有したことのある人なら、雲も月もない夜に感じる期待感は誰でも理解できるでしょう。湿気が多く...
4000年前の歯からペストのDNAが発見された
ペストとして知られる持続性病原体は、約2500万人の死者を出す何世紀も前からヨーロッパやアジアで蔓延...
腕が短いTレックスの親戚は小惑星が衝突するまで繁栄していた
古生物学者は、モロッコでティラノサウルス・レックスの近縁種の新種の化石2種を発見した。有名なT・レッ...
ロボットは自由に行動し、多様な集団に進化する
進化を研究する方法はいくつかあります。孤立した人口で淡水もない小さな島のテントで何ヶ月も暮らすことも...
最も古い唐辛子の標本は現在のコロラド州のものかもしれない
ナス科の植物のない生活を想像するのは難しい。トマト、ジャガイモ、ピーマン、ナスなど、健康的な食事やお...
奇妙な小惑星と彗星のハイブリッドは46億年前に遡る
ケンタウルス族は実在する。宇宙ではそうだ。これらの天体は木星と海王星の間を太陽の周りを回っており、小...
#Scikus: ポピュラーサイエンス読者による 12 の素敵な科学俳句
先週の金曜日、ちょっとした楽しみとして、Facebook と Twitter のフォロワーに、科学俳...
絶滅した類人猿の内耳に、人類が直立歩行を学んだ経緯の手がかりが隠されている
一部の霊長類が四足歩行から二足歩行に進化した経緯をたどるのは困難だった。化石記録は必ずしも二足歩行の...
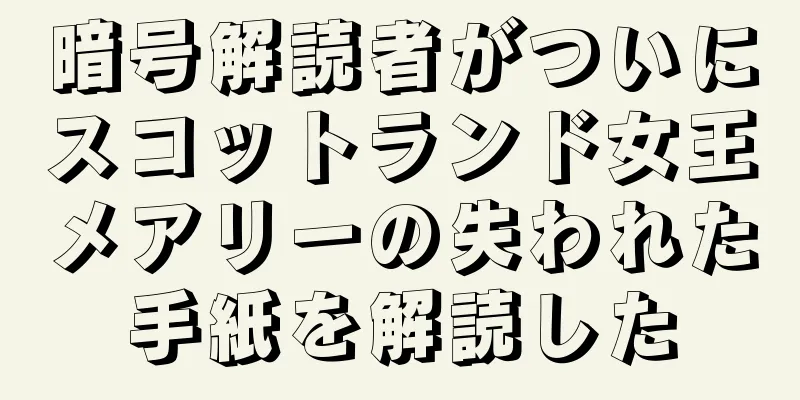
![ビッグピクチャー:シミュレーションによるブラックホールの衝突が天の川銀河を切り裂く [アニメーション]](/upload/images/67d4f7846c223.webp)