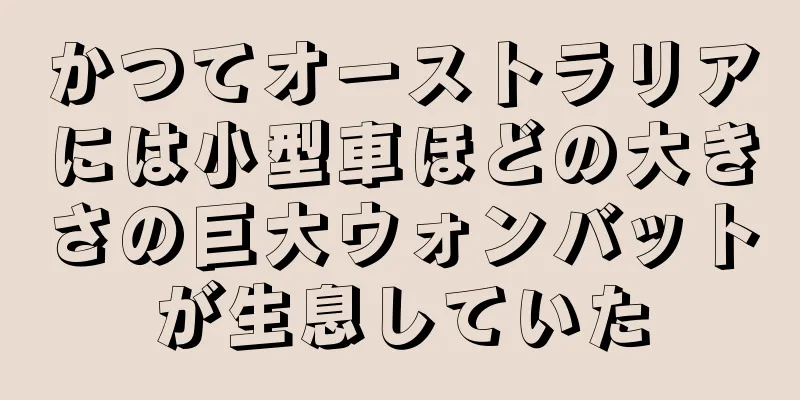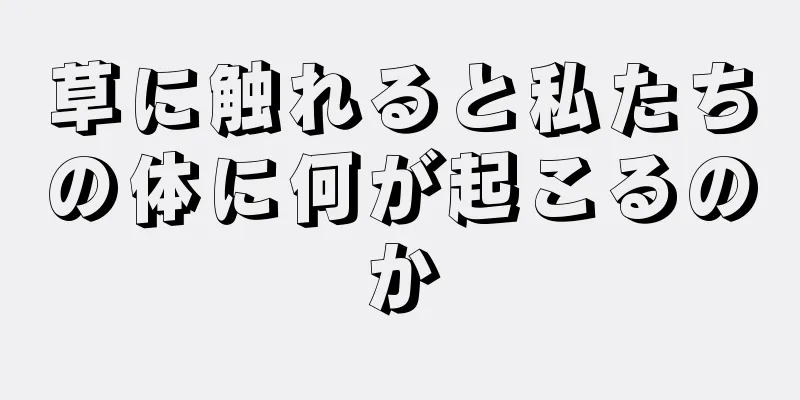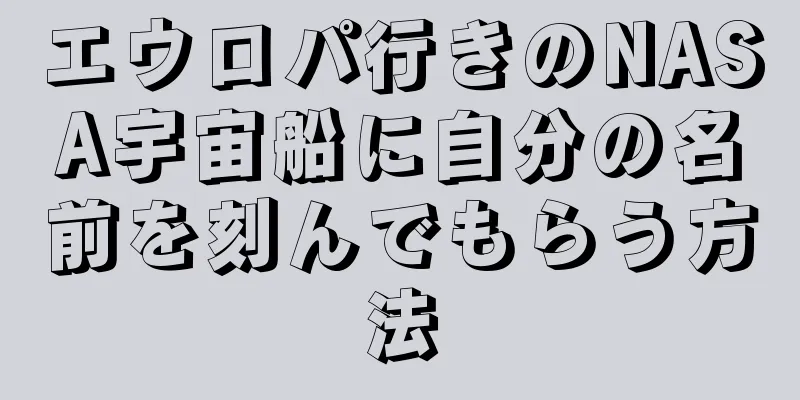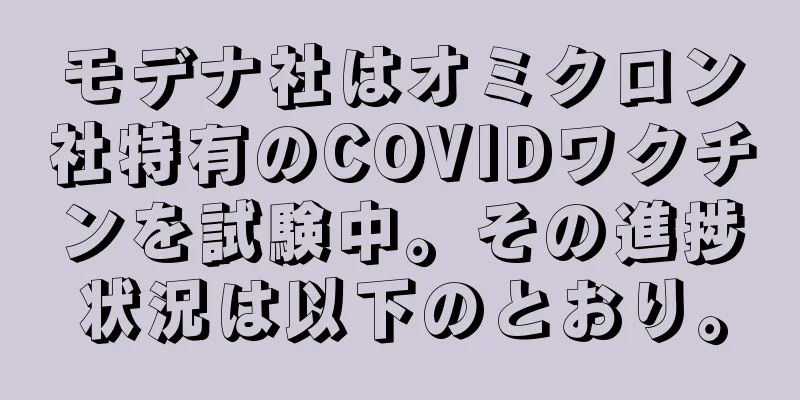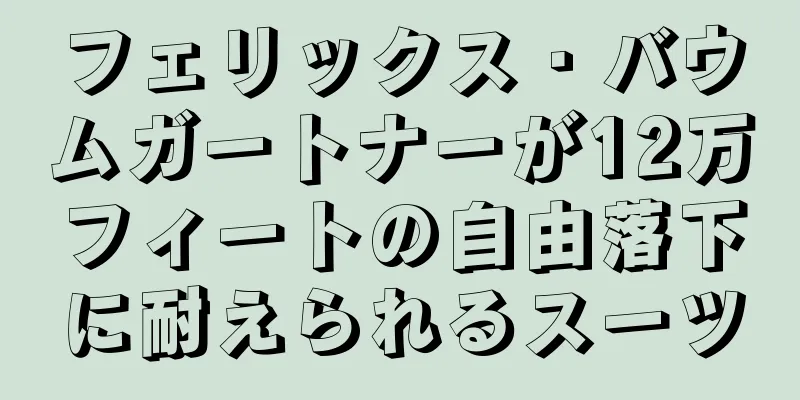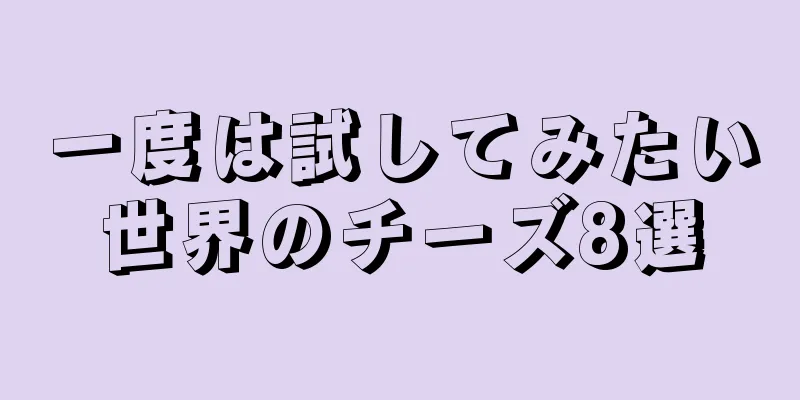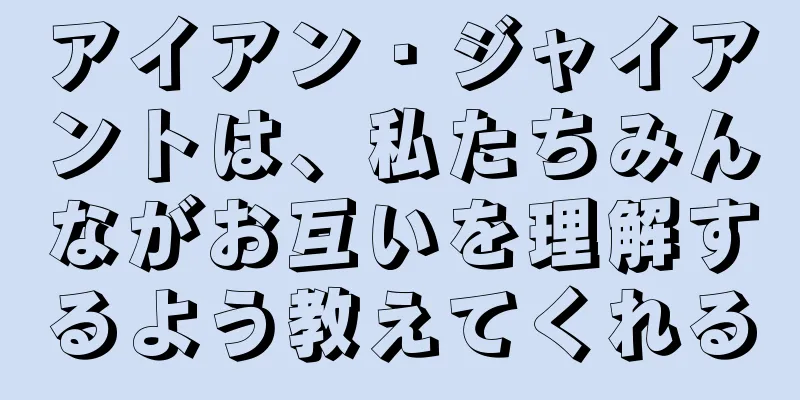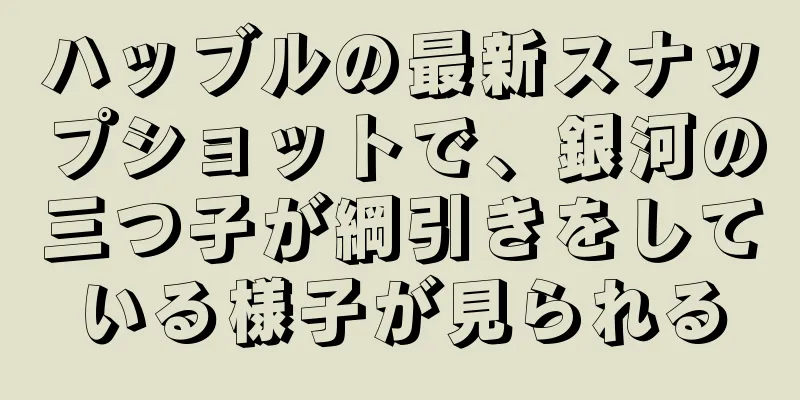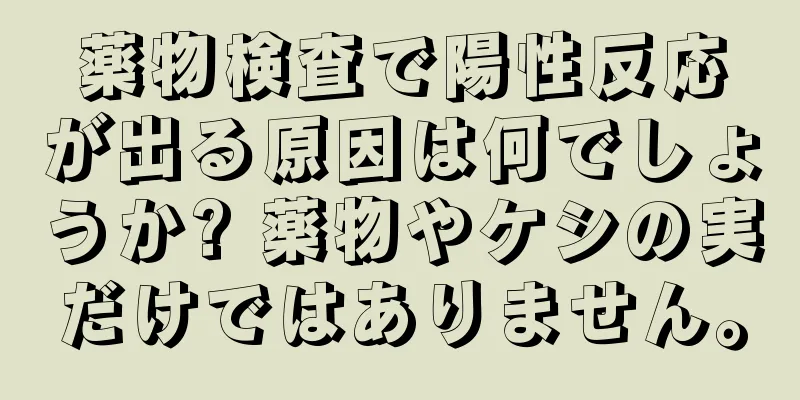我々の最も近い隣の恒星系は住むにはひどい場所のようだ
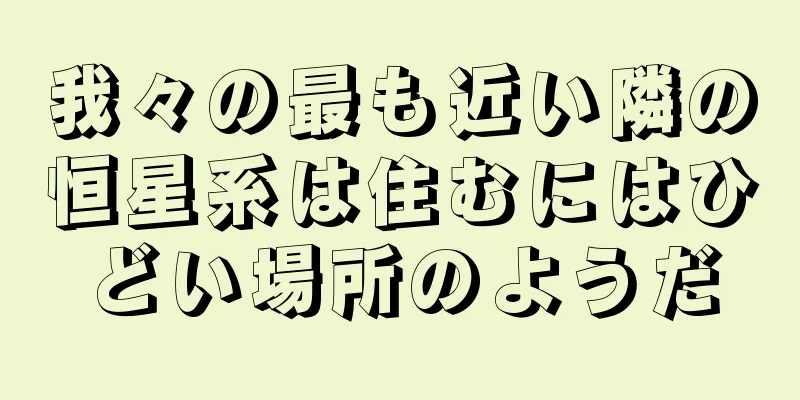
|
地球から 4 光年ほど離れたところに、恒星の周りをちょうどよい距離 (近すぎず遠すぎず) で周回する惑星があります。その惑星の表面に液体の水が存在する可能性があります。その惑星の大気についてはほとんどわかっていません (大気があるかどうかさえも)。内部についてさらに詳しく調べようとしています。まだ解明すべきことはたくさんありますが、異星人の隣人を見つけるには有望な場所であるように聞こえませんか? 巨大な恒星フレアにどう対処するかがわかれば良いのですが。 今週、天体物理学ジャーナルレターズに掲載された研究によると、昨年秋の研究報告にあるように、恒星の周囲に暖かい塵の輪があり、惑星の快適な育成場である可能性があったが、実際には巨大な恒星フレアがあったことが判明した。(これは太陽フレアと同じだが、太陽以外の恒星で起こる)。 カーネギー研究所で他の恒星の周りの破片円盤を研究している天体物理学者メレディス・マクレガー氏が最初に興味を持ったのは、この塵の研究だった。 「太陽系には円盤があり、小惑星帯とカイパーベルトがありますが、これらは太陽系が形成された際に残った物質だと考えられています。他の星を見て同じ構造を見ることができるのはとても興味深いことです」とマグレガー氏は言う。 彼女は以前にもプロキシマ・ケンタウリのような恒星を観察したことがあり、それらの恒星が信じられないほど活発で、他の恒星系の塵の検出によく使われるミリメートル波長を含む多くの光の波長にわたって放射線を多く含んだフレアを頻繁に放出している可能性があることを知っていた。 「この観測中に星が大きな活動を起こした可能性があるかどうか、そしてそれが結果に影響を与えたかどうか興味がありました」とマクレガー氏は言う。 そこで彼女は、前回の研究で使用されたデータを詳しく調べることにした。研究チームは、3か月にわたって行われた15回の観測、合計10時間のプロキシマ・ケンタウリの観測データを使用した。そのほとんどの期間、この星は静かだった。 「ほとんどの観測では、この星は特に目立った動きは見せませんでした」とマグレガー氏は言う。「しかし、2分間だけこの星は大きく明るくなり、時間の経過とともに光束の変化をたどることができます。」 その短期間の明るさの上昇は恒星フレアだった。マグレガー氏によると、前回の研究では観測結果を総合的に検討し、明るさの上昇は内部付近の恒星で温められた塵の環を含む潜在的な惑星系であると解釈した。アルマ望遠鏡が探しているのはまさにそれだ。特に、電子レンジから放射される電磁波に似たミリ波の波長の信号を探している。 「私たちは、さまざまな波長を観測することで、さまざまな大きさの粒子の集団を調査しています」とマグレガー氏は言います。「システムを観測するときに使用するルールは、観測している光の波長が、観測している粒子のサイズであるということです。つまり、ミリメートルの波長では、ミリメートルサイズの塵粒子や氷粒子を追跡しているのです。」 これは恒星系の基礎構造を理解する上で重要です。しかし、恒星フレアや太陽フレアなど、ミリメートル波長で現れる現象は他にもたくさんあります。 「このフレアの絶対的な明るさを太陽フレア(ミリ波)と比較すると、プロキシマ・ケンタウリで観測されたこのフレアは太陽で観測されるものより10倍明るい」とマクレガー氏は言う。しかし、これはこの太陽フレアが太陽のフレアより10倍大きかったという意味ではない。この比較はミリ波のみで、フレアイベントによって放出される他のすべての形態の放射線は対象としていない。さらに、太陽とプロキシマ・ケンタウリは、同じクラスの恒星でさえない。 「プロキシマ・ケンタウリはM型矮星で、はるかに小さい星ですが、磁場がはるかに強いです。2つの異なる種類の星をどのように比較するかについては、まだ多くのことを学んでいるところです」とマグレガー氏は言う。 プロキシマ・ケンタウリ系で塵を発見した研究の筆頭著者で天体物理学者のギレム・アングラダ氏も同意見だ。「これは重要な結果であり、M型矮星の大気の挙動をより深く理解するのに役立つ可能性があります。プロキシマ・ケンタウリは太陽に最も近い恒星であるため、より遠い恒星について学ぶための優れた実験室となります」とアングラダ氏は電子メールで述べている。 プロキシマ・ケンタウリは、地球に最も近い恒星であり、液体の水が存在するのにちょうどよい軌道に惑星があるため、注目を集めている。しかし、太陽フレアが増加するにつれ、プロキシマbに大気があるかどうかは疑わしくなっている。大気は液体の水を維持するために不可欠である。 「私たちはアルマ望遠鏡で10時間の観測時間中にこのフレアを1回だけ捉えました。これは非常に幸運な出来事か、あるいはこの規模のフレアがプロキシマ・ケンタウリでかなり頻繁に発生している可能性があります」とマクレガー氏は言う。「それは惑星の大気にとって悪いことを意味する可能性が高いと私は断言します。」 大規模な太陽フレアは、通常、コロナ質量放出、つまり太陽からの熱せられた荷電粒子の巨大な噴出を伴う。もし CME がケンタウリのフレアを伴うと、その組み合わせは惑星に放射線を浴びせるだけでなく、大気を剥ぎ取る可能性がある。 「M型矮星のフレアがコロナ質量放出を伴うかどうかはまだわかっていません。それは一種の未解決の問題です」とマグレガー氏は言う。 アングラダ氏によると、彼と彼の同僚は、マクレガー氏の研究とは別に、その後のデータ分析で予期せずフレアを発見したという。「私たちの新しい推定では、塵の量は以前の推定の約半分である可能性があるが、この値を確認する作業はまだ進行中です。一方、マクレガー氏らの論文では、プロキシマ・ケンタウリの近辺の環境には塵が存在しない可能性があることが示唆されています。この 2 つの研究は、探索プログラムで得られた限られたデータセットを使用して実施されました。より感度の高い新しい観測により、システムの構造と主要な特性を確実に確立する高解像度の画像が得られる可能性があります」とアングラダ氏は言う。 プロキシマ・ケンタウリには一般の人々と科学界の両方から大きな関心が寄せられており、新たな観測が確実に行われるでしょう。 「多くの疑問に答える必要があります。この新しい結果と ALMA による以前の報告は、私たちが最も近い隣人についてほとんど何も知らないこと、そしてデータの解釈には特に慎重かつ徹底する必要があることを示しています」と、プロキシマ b の発見に貢献したが最新の研究には関わっていない天体物理学者のギエム・アングラダ・エスクード氏は言う。(ギエム・アングラダ氏とは無関係) それらの疑問には、フレアはどのくらいの頻度で発生するのか、その性質は何か、プロキシマ システムのさらに外側にもっと冷たいデブリ ディスクが存在する可能性があるのか、プロキシマ b は実際どのようなものなのか、それに惑星があるのか、などが含まれます。これらの答えはどれも簡単には得られませんが、だからこそ答えを探すのがさらにエキサイティングになります。 2018年3月2日 この投稿はGuillem Angladaからのコメントで更新されました |
<<: ヘビー級であることだけでは褐色矮星を恒星に変えるには不十分
>>: 『オデッセイ』の著者アンディ・ウィアーが火星についての質問に答える
推薦する
ハリウッドが世界を殺人小惑星から救うことについて間違っていること、そして意外にも正しいこと
ハリー・スタンパーが世界を救ったとき、あなたはどこにいましたか?当時私は10歳でしたが、昨日のことの...
月はかつてマグマの海に覆われていた:新たなデータがその説を裏付ける
約 45 億年前、テイアと呼ばれる火星サイズの原始惑星に、大変な出来事がありました。その軌道は、別の...
先史時代のトカゲは二足歩行で走ることができた
1億1千万年前、白亜紀後期、トカゲは現在の韓国の泥沼を歩き回っていた。捕食性の翼竜がちょっとしたごち...
バイオエンジニアリングされた寄生虫が将来、脳に薬を届けるかもしれない
トキソプラズマ原虫に意図的に感染することは、医療行為として推奨されていません。ほとんどの人は目立った...
カッシーニは土星の大気圏に突入しました。太陽系探査の今後はどうなるのでしょうか?
カッシーニは、間もなく宇宙船を塵と化してしまう大気の力と格闘しながら、最後の瞬間までデータを送信し続...
1939年の世界はどうなるのか
世界は火で終わるという人もいれば、氷で終わるという人もいます。1939 年の科学者たちは、そのリスト...
日本の宇宙船が小惑星に弾丸を発射する理由
地球から約1億8千万マイル離れたところに、直径約0.6マイルの小さな小惑星「リュウグウ」があり、約1...
ペンギンの多様な外見は島々のおかげかもしれない
ペンギンといえば、南極の海氷の上をよちよちと歩く、象徴的な皇帝ペンギンを思い浮かべることが多い。しか...
新しい理論により、知的なエイリアンが存在する可能性が高まった
私たち(人間)がここ(地球)にたどり着くまでに、実に多くの出来事が起こりました。私たちの種族は、水で...
生命の明るい顕微鏡画像 6 枚
顕微鏡とカメラのメーカーであるオリンパス社は、10 年連続で光学顕微鏡写真コンテストを主催しており、...
火星人と話す
ハリウッドでは『オデッセイ』のような映画はめったに作られない。これは宇宙を舞台にした大予算のSF映画...
真剣に、プラスチックで食べ物を電子レンジで温めるのはやめましょう
冷蔵庫や食品庫の中には、プラスチックが至る所にあります。もちろん、ラップ、保存袋や容器、クラムシェル...
なぜ人によっては睡眠時間が短くて済むのでしょうか?
私たちのほとんどは、7 時間未満の睡眠は、眠気や思考力の低下、ベッドに戻りたくなる衝動に駆られます。...
『パッセンジャー』の冬眠科学は現実とそれほどかけ離れていない
人類が別の惑星へ旅立つ前に(そしてその日はもうすぐ来るかもしれないが)、ある疑問に答えなければならな...
ホッキョクグマはわずか7万年前に北極に適応した
北極は地球上で最も住みやすい場所ではない。トナカイなど北極の動物の中には、そこで繁栄するためにいくつ...